中古住宅の固定資産税はいつから払う?
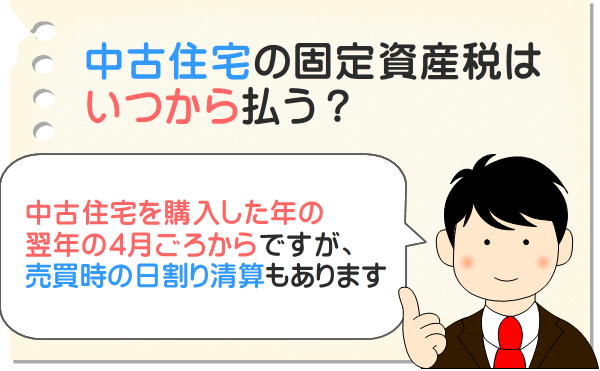
中古住宅を購入するといつから固定資産税を払うか気になりますが、中古住宅を購入した年の翌年の4月ごろから納税することとなります。
また、中古住宅を購入する際は、その年のその日以降の固定資産税を売り主に清算するのが通例です。
中古住宅の購入を希望される方へ向けて、いつから固定資産税を払うかご紹介しましょう。
目次
- 1. 翌年の4月ごろから払う
- 2. 売買時の固定資産税の日割り清算
- 3. 中古住宅の固定資産税はいくら?
- 3-1. 一戸建て中古住宅の固定資産税を試算
- 4. 中古住宅の固定資産税の調べ方
- まとめ - 市街地の中古住宅には都市計画税もかかる
1. 翌年の4月ごろから払う
中古住宅を購入する際は固定資産税をいつから払うか気になりますが、中古住宅を購入した年の翌年の4月ごろからです。
固定資産税は1月1日の時点で住宅や土地などの不動産を所有する方に課せられ、その1月1日が属する年の4月ごろに一括で納税する、または4月ごろから翌年の2月ごろにかけて4回に分納します。
よって、中古住宅を購入しつつ固定資産税を支払うのは、中古住宅を購入した年の翌年の4月ごろからとなります。
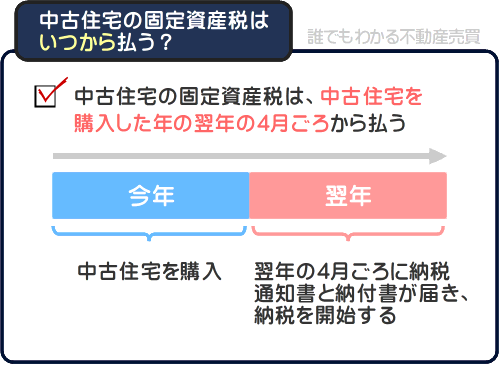
4月ごろからというと時期があいまいですが、固定資産税はその不動産が所在する市町村に収める地方税であり、各市町村によって納付期限が異なることが理由です。
とはいうものの、多くの市町村では4月上旬ごろに納税通知書と納付書が届き、一括で納付する場合の期限と、4回に分納する場合における第1回目の納付期限は4月末となっています。
固定資産税の主な納付期限は以下のとおりであり、購入する中古住宅の固定資産税の正確な納付期限は、その中古住宅が所在する市町村の公式サイト内に設けられた検索窓に「固定資産税
納期」などと入力しつつ検索することにより確認することが可能です。
固定資産税の納付期限
| 支払い方法 | 納付期限 |
|---|---|
| 一括 | 4月末、または5月末など |
| 分納 第一期 | 4月末、または5月末など |
| 分納 第二期 | 7月末、または8月末など |
| 分納 第三期 | 12月末など |
| 分納 第四期 | 翌年の2月末など |
なお、中古住宅の固定資産税は物件を購入した年の翌年の4月ごろから市町村に納付しますが、中古住宅を購入する際は、その年のその日以降の固定資産税を売り主に清算するのが通例です。
続いて、中古住宅を購入する際に売り主に清算する固定資産税の詳細をご説明しましょう。
2. 売買時の固定資産税の日割り清算
この記事の「1. 翌年の4月ごろから払う」にてご紹介したとおり、固定資産税は1月1日の時点で不動産を所有する方に課せられ、その1月1日が属する年の4月ごろから納税します。
そのため、中古住宅が売買される年の固定資産税は売り主に納税通知書と納付書が届き、売り主が納税することとなります。
しかし、それでは中古住宅の売り主は手放した不動産の固定資産税を支払うこととなり、公平ではありません。
よって、中古住宅を売買する際は、その年の固定資産税を日割り計算し、その年のその日以降の固定資産税を買い主が売り主に清算するのが通例となっています。
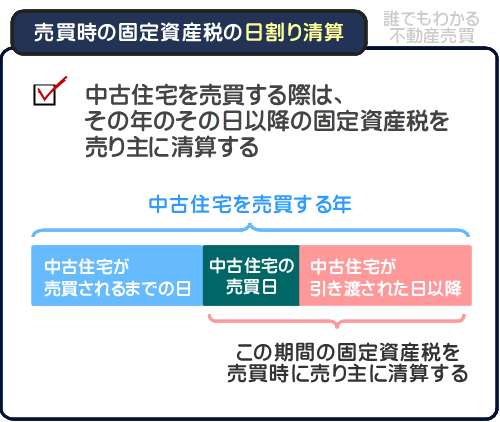
たとえば、その中古住宅のその年の固定資産税が10万円であり、7月1日に売買される場合は10万円÷365日×183日=50,142円と計算し、50,142円を買い主が売り主に清算するといった具合です。
そして、中古住宅を売買した年の翌年の4月ごろに固定資産税の納税通知書と納付書が買い主の自宅に届き、買い主が市町村に固定資産税を納税することとなります。
3. 中古住宅の固定資産税はいくら?
中古住宅の固定資産税はいつから払うか気になりますが、中古住宅を購入した年の翌年の4月ごろからです。
また、中古住宅を購入する際は、その年のその日以降の固定資産税を売り主に清算する必要もあります。
そこで気になるのが税額ですが、築年数が新しく立地条件が良ければ15万円以上など、築年数が古く立地条件が芳しくなければ5万円程度などが通例です。
一戸建ての中古住宅を購入すると建物と土地を所有することとなり、その両方に固定資産税が課せられます。
中古マンションを購入した場合は一戸部分とその中古マンションが建つ敷地を戸数などで割った面積の土地(これ以降は土地の持ち分と呼びます)を所有することとなり、その両方に固定資産税が課せられます。
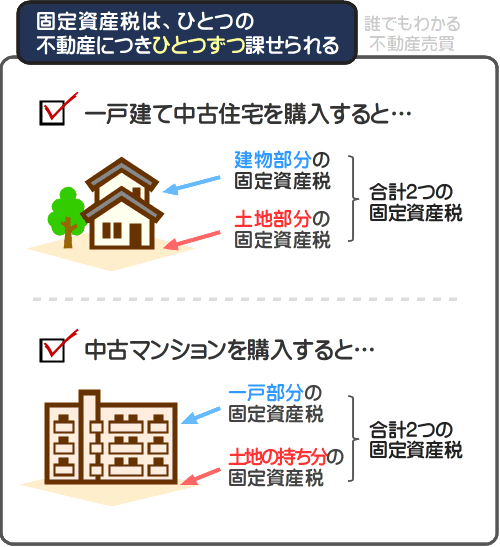
そして、各固定資産税は課税標準額に固定資産税の税率を掛け算しつつ税額が決定され、具体的な計算式は以下のとおりです。
固定資産税の計算式
課税標準額×税率=固定資産税
式に含まれる税率は、市町村によって異なるものの主に1.4%です。
くわえて、式には課税標準額という聞きなれない言葉が含まれますが、課税標準額は主に固定資産税評価額となっています。
固定資産税評価額とは、固定資産税を計算するために市町村が評価したその不動産の価格であり、固定資産税評価額は売買価格より安くなるのが通例です。
たとえば、築15年であり売買価格が1,500万円の一戸ての中古住宅であれば、建物部分の固定資産税評価額は400万円程度、土地部分の固定資産税評価額は500万円程度などとなります。
また、築15年であり売買価格が1,500万円の中古マンションであれば、一戸部分の固定資産税評価額は600万円程度、土地の持ち分の固定資産税評価額は350万円程度などです。
ただし、住宅が建つ土地には住宅用地の特例が適用され、課税標準額は固定資産税評価額の6分の1などとなります。
課税標準額や固定資産税評価額、住宅用地の特例など難解であり、固定資産税に興味がない方はよくわかりません。
そこで、築15年、売買価格が1,500万円、建物部分の固定資産税評価額が400万円、土地部分の固定資産税評価額が500万円の一戸建て中古住宅の固定資産税を試算してみましょう。
3-1. 一戸建て中古住宅の固定資産税を試算
それでは、売買価格が1,500万円、築15年、建物部分の固定資産税評価額が400万円、土地部分の固定資産税評価額が500万円の一戸建て中古住宅の固定資産税を試算します。
まずは、建物部分にかかる固定資産税を計算しましょう。
固定資産税評価額が400万円の建物部分の固定資産税は「400万円×1.4%=56,000円」と計算し、税額は56,000円です。
建物部分の固定資産税の計算式
400万円(建物部分の固定資産税評価額)×1.4%(税率)=56,000円
つぎに、固定資産税評価額が500万円である土地部分の固定資産税を計算します。
本来であれば土地の固定資産税は、その固定資産税評価額に1.4%などの税率を掛け算した額ですが、住宅が建つ土地には「住宅用地の特例」と呼ばれる特例が適用され、固定資産税評価額の6分の1などに税率を掛け算しつつ税額を計算することとなります。
具体的な計算式は、以下のとおりです。
土地部分の固定資産税の計算式
500万円(土地部分の固定資産税評価額)×6分の1(住宅用地の特例)×1.4%(税率)=11,666円
上記のように計算し、土地部分の固定資産税は11,666円となります。
この土地部分の固定資産税である11,666円と、先に計算した建物部分の固定資産税である56,000円を合計した67,666円が、売買価格が1,500万円、築15年の一戸建て中古住宅の固定資産税の試算結果です。
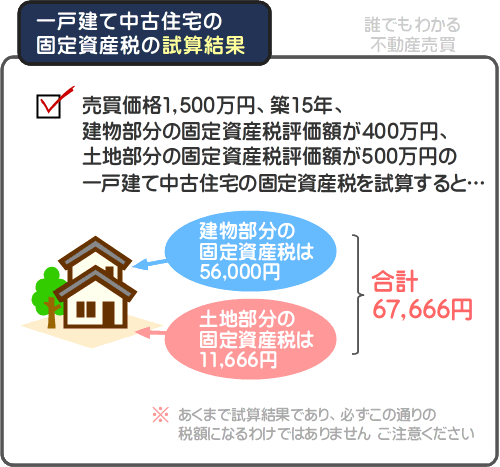
ちなみに、私が運営するもう一つのサイト「固定資産税をパパッと解説」では、不動産の固定資産税に関する様々なことをわかりやすく解説しています。
中古住宅の購入をご予定になりつつ固定資産税をいつから払うか気になる方や、固定資産税の制度そのものに興味のある方がいらっしゃいましたら是非ご覧ください。
固定資産税をわかりやすく解説!
固定資産税をパパッと解説
4. 中古住宅の固定資産税の調べ方
この記事の「3. 中古住宅の固定資産税はいくら?」にてご紹介したように、中古住宅の固定資産税は課税標準額に税率を掛け算しつつ計算します。
しかし、実際に税額を計算するためには、その中古住宅の固定資産税評価額を調べる必要があるなど手順が複雑です。
その中古住宅の固定資産税評価額は、その物件が所在する地域を管轄する市町村役場にて固定資産課税台帳を閲覧することにより確認できますが、物件の所有者以外が同台帳を閲覧するためには物件の所有者の委任状が必要となります。
そのため、販売されている中古住宅の固定資産税が気になる場合は、その物件を仲介する不動産業者に税額を問い合わせるのが良いでしょう。
大抵の不動産業者は、こちらの身分を明かさずとも固定資産税くらいは教えてくれます。
ただし、アットホームなどの不動産検索サイトに設けられた問い合わせフォームから問い合わせる場合は、こちらの電話番号を不動産業者に知らせる必要があるため注意してください。
また、大抵の不動産業者は固定資産税を問い合わせても即答は期待できず、折り返しによる連絡で税額が知らされます。
不動産業者は多くの中古住宅を取り扱うため、全ての物件の固定資産税を即答することは難しく、資料を確認するなどして税額が知らされることとなります。
まとめ - 市街地の中古住宅には都市計画税もかかる
中古住宅の固定資産税はいつから払うかご紹介しました。
固定資産税は1月1日の時点で住宅や土地などの不動産を所有する方に課せられ、その1月1日が属する年の4月ごろから納税します。
よって、中古住宅の固定資産税は、中古住宅を購入した年の翌年の4月ごろから払うこととなります。
ただし、中古住宅を売買する際は、その年のその日以降の固定資産税を日割り計算しつつ売り主に清算する必要があるため留意してください。
また、固定資産税は課税標準額に固定資産税の税率を掛け算しつつ税額が決定されますが、計算方法が複雑です。
よって、購入を希望する中古住宅の固定資産税を把握したいと希望しつつも上手く試算できない場合は、その物件を取り扱う不動産業者にお問い合わせください。
即答は期待できませんが、簡単に固定資産税を調べることが可能です。
なお、市街地に位置する中古住宅を所有すると、固定資産税に加えて都市計画税も課せられます。
都市計画税とは市街地の道路の整備費用などを賄うために徴収される目的税であり、以下の式で計算しつつ税額が決定されます。
都市計画税の計算式
課税標準額×都市計画税の税率=都市計画税
式に含まれる課税標準額は、固定資産税を計算する式に含まれる課税標準額と同じく「その不動産の固定資産税評価額」であり、都市計画税の税率は0.3%です。
固定資産税の税率は1.4%であるのに対し、都市計画税の税率は約5分の1である0.3%のため、都市計画税額は固定資産税額の約5分の1となります。
都市計画税は1月1日の時点で市街地に不動産を所有する方に課せられるため、市街地に位置する中古住宅を購入した場合は、物件を購入した年の翌年の4月ごろから固定資産税と一緒に都市計画税を納税することとなります。
ご紹介した内容が、中古住宅の固定資産税をいつから払うかお調べになる皆様に役立てば幸いです。失礼いたします。
最終更新日:2021年8月
記事公開日:2019年8月
こちらの記事もオススメです
