すまい給付金が貰えない!?中古住宅の受給条件を再度見直し
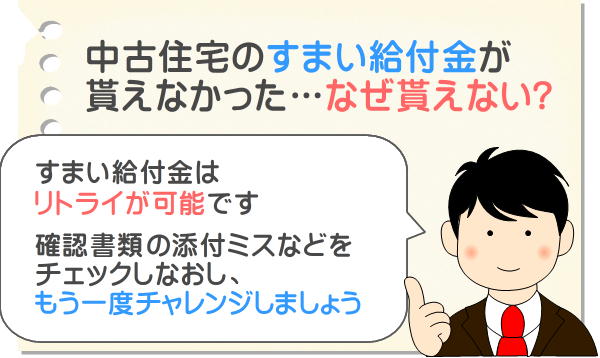
すまい給付金とは、一定の条件を満たす住宅を購入することにより最高50万円が支給される補助金であり、新築だけではなく中古住宅を購入した場合も受給できます。
しかし、中古住宅の受給条件は新築より複雑であり、中古住宅を購入しつつ申請をしたものの補助金が貰えないとお嘆きの方が少なからずいらっしゃるようです。
そこで、今回の「誰でもわかる不動産売買」では、中古住宅を購入しつつ申請したものの補助金が貰えなかった方へ向けて、リトライ時のバイブルとなるよう受給条件を再度確認しましょう。
目次
- 1. すまい給付金の中古住宅の条件をクリアしていない
- 2. 年収が高く扶養家族が少ない
- 3. 中古住宅に持ち分がない
- 4. 50歳未満で現金一括購入
- 5. 申請書と確認書類に不備があった
- まとめ - 国土交通省では電話サポート実施中
1. すまい給付金の中古住宅の条件をクリアしていない
すまい給付金が受給できる中古住宅の条件は、すまい給付金の公式サイト内のページ「すまい給付金|対象要件(中古住宅)」にて確認できますが、「既存住宅売買瑕疵保険へ加入する中古住宅を購入する」など、満たすことが難しい条件が含まれています。
そのため、すまい給付金が貰えないとお困りであれば、購入した中古住宅が受給条件を満たさなかったのかもしれません。
まずは、すまい給付金が受給できる中古住宅の条件を確認しましょう。
1-1. 売主が不動産業者の中古住宅を購入する
売りに出されている中古住宅は、以下の2つに大きく分類されます。
- 1. 個人が宅地建物取引業者(不動産業者)を仲介させつつ売りに出す中古住宅
- 2. 宅地建物取引業者が直接販売する中古住宅
売りに出されている中古住宅の多くは1の「個人が宅地建物取引業者を仲介させつつ売りに出す中古住宅」ですが、すまい給付金を受給するためには、2の「宅地建物取引業者が直接販売する中古住宅」を購入しなければなりません。
購入した中古住宅が2に該当するかは、物件代金に消費税が掛かったか否かによって確認できます。
1の「個人が宅地建物取引業者を仲介させつつ売りに出す中古住宅」には消費税が掛かりませんが、2の「宅地建物取引業者が直接販売する中古住宅」には消費税が掛かります。
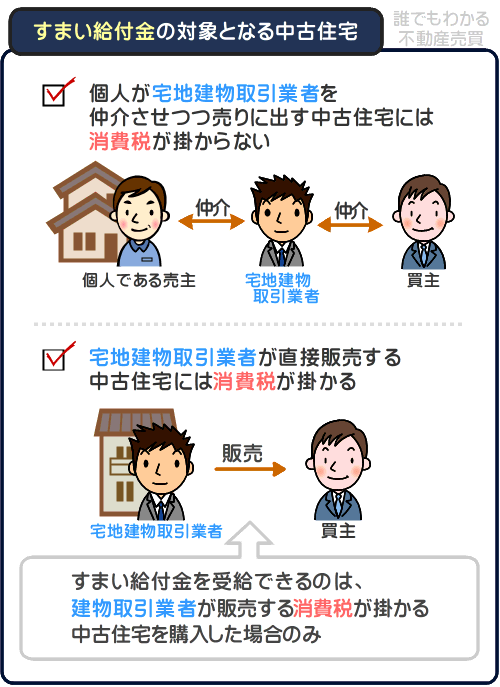
すまい給付金が受給できる条件を満たすのは、宅地建物取引業者が直接販売する中古住宅を購入した場合のみです。
すまい給付金の受給を申請しつつ補助金が貰えないとお嘆きの場合は、宅地建物取引業者が直接販売する中古住宅を購入したかご確認ください。
ちなみに、1の「個人が宅地建物取引業者を仲介させつつ売りに出す中古住宅」には消費税が掛かりませんが、仲介手数料が掛かります。
よって、仲介手数料を支払った記憶があるのであれば、1の「個人が宅地建物取引業者を仲介させつつ売りに出す中古住宅」を購入した可能性が高いといえるでしょう。
1-2. 登記簿の床面積が50平方メートル以上の中古住宅を購入する
すまい給付金を受給するためには、床面積が50平方メートル以上(令和2年12月1日から令和3年11月30日までに売買契約を締結した場合は40平方メートル以上)の中古住宅を購入する必要があります。
この50平方メートル、または40平方メートルですが、中古住宅の資料や売買契約書などに記されている床面積ではありません。
その中古住宅の登記簿に記載された床面積が50平方メートル、または40平方メートル以上の必要があります。
登記簿とは、その不動産の所在地や所有者、構造、床面積などが記された法務局に設置されている公の帳簿であり、登記簿に記されている床面積は実測値と必ず一致するとは限りません。
たとえば、現場で寸法を取ると床面積は50平方メートルであっても、登記簿には48平方メートルと記されている場合があります。
登記簿に記されている床面積は、登記事項証明書にて確認できます。
登記事項証明書とは登記簿の内容を写した書面であり、法務省が公開する建物の登記事項証明書の見本は以下のとおりです。
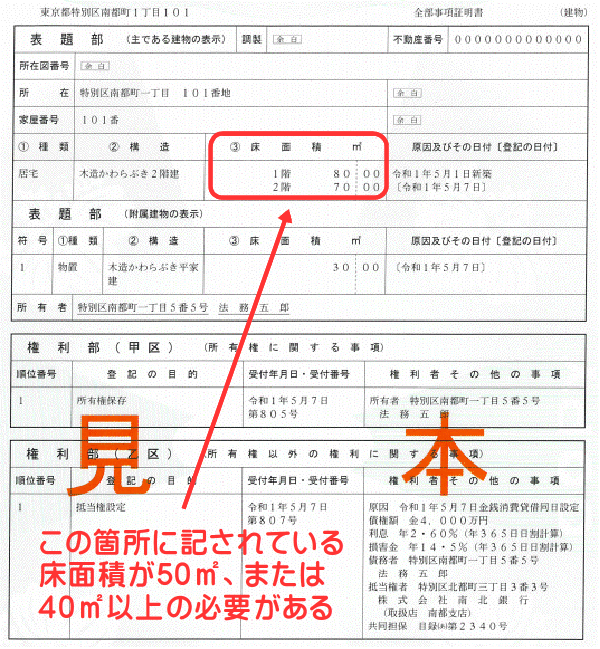
登記事項証明書は購入した中古住宅が所在する地域を管轄する法務局などにて入手できますが、中古住宅を購入後に司法書士から手渡し、または郵送にて受け取ることもあります。
また、すまい給付金の申請を行う際は、登記事項証明書の提出を求められます。
よって、すまい給付金を申請しつつ補助金が貰えないとお嘆きの場合は、提出した書類に登記事項証明書が含まれていたはずです。
すまい給付金を申請しつつも補助金が貰えないのであれば、もう一度登記簿に記されている中古住宅の床面積をご確認ください。
なお、すまい給付金を申請する際は登記事項証明書の提出を求められますが、一戸建ての中古住宅には建物部分と土地部分の登記事項証明書があり、提出を求められるのは建物部分の登記事項証明書です。
そして、コピーではなく登記事項証明書そのものの提出を求められます。
よって、一戸建ての中古住宅を購入し、すまい給付金を申請したものの補助金が貰えない場合は、建物部分の登記事項証明書の原本を提出したか再度ご確認ください。
ちなみに、中古マンションの登記事項証明書には、建物部分と土地部分の区別はありません。
1-3. 売買時等の検査
すまい給付金が受給できる条件は、すまい給付金の公式サイト内に設けられたページ「すまい給付金 | 対象要件(中古住宅)」にて確認できますが、その下部に記されている「売買時等の検査」という項目が最も難解です。
その項目には、すまい給付金を受給するためには、以下の3つのいずれかの条件を満たした中古住宅を購入しなければならないと記されています。
- 既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅
- 既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)
- 建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険(人の居住の用に供したことのない住宅を目的とする住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅
上記の3つの条件は特に難解であり、すまい給付金が貰えないとお嘆きであれば条件を満たさなかった可能性があります。
ここから、3つの条件をわかりやすく解説しましょう。
既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅
既存住宅売買瑕疵保険とは、国土交通省が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人のみが取り扱う中古住宅専用の保険です。
既存住宅売買瑕疵保険に加入する中古住宅は、引き渡し後に耐力性の欠如や雨漏りなどの重大な欠陥が発見されれば、その修繕費用を保険法人が負担します。
つまり「既存住宅売買瑕疵保険に加入する中古住宅」とは、引き渡し後に重大な欠陥が見つかった場合、その修繕費用が保険法人から支払われる保証付きの中古住宅という意味です。
既存住宅売買瑕疵保険に加入する中古住宅には保険付保証明書が付属され、そのコピーは、すまい給付金の受給を申請する際の必要書類として活用できます。
以下は、既存住宅売買瑕疵保険の相談窓口となる住宅瑕疵担保責任保険協会が公開する既存住宅売買瑕疵保険の紹介動画です。
動画のタイトルは「中古住宅かし保険」ですが、中古住宅かし保険とは既存住宅売買瑕疵保険を意味します。
既存住宅売買瑕疵保険の紹介動画
既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)
既存住宅性能表示制度とは、国土交通大臣が登録した登録住宅性能評価機関が、中古住宅の耐震性、雨漏りやシロアリによる食害、給排水管の腐朽、換気扇の動作不良の有無などを調査し、既存住宅性能評価書としてまとめる制度です。
つまり、「既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)」とは、既存住宅性能評価書が付随し、なおかつその既存住宅性能評価書に耐震等級が1以上であることが記された中古住宅というわけです。
この条件は、耐震等級が1以上であることが記されている既存住宅性能評価書が付随する中古住宅を購入し、既存住宅性能評価書のコピーを確認書類としてすまい給付金の窓口に提出することによりクリアできます。
ただし、既存住宅性能評価書には、耐震性が記されている場合と記されていない場合があるため注意してください。
耐震性が記されていない既存住宅性能評価書のコピーは、確認書類として受け付けられません。
なお、既存住宅性能評価書に耐震等級が1以上であることが記されていない場合でも、その中古住宅に免震装置が付き、なおかつそのことが既存住宅性能評価書に記されていれば、「既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)」という条件をクリアすることが可能です。
詳細は、すまい給付金が公開する資料「すまい給付金|申請の手引き」の20ページ「既存住宅性能表示制度を利用している場合」にてご確認いただけます。
建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険(人の居住の用に供したことのない住宅を目的とする住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅
この条件は特に難解ですが、「築年数が10年以内であり住宅瑕疵担保責任保険に加入する中古住宅」または「築年数が10年以内であり建設住宅性能表示制度を利用する中古住宅」を購入することにより、すまい給付金を受給する条件を満たします。
それぞれの詳細は、以下のとおりです。
- 築年数が10年以内であり住宅瑕疵担保責任保険に加入する中古住宅
- 住宅瑕疵担保責任保険とは、国土交通大臣が指定した住宅瑕疵担保責任保険法人のみが取り扱う新築住宅専用の保険です。
住宅瑕疵担保責任保険の保険期間は10年であり、同保険に加入する新築を購入しつつ10年以内に欠陥が見つかれば、住宅瑕疵担保責任保険法人から修繕費用が支払われます。
つまり、築年数が10年以内であり住宅瑕疵担保責任保険に加入する中古住宅とは、住宅瑕疵担保責任保険の保険期間が切れていない築年数が10年以内の中古住宅というわけです。
住宅瑕疵担保責任保険に加入する新築には、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した付保証明書が付随されます。
そして、この付保証明書のコピーは、中古住宅におけるすまい給付金の受給を申請する際の添付書類として活用できます。
よって、「築年数が10年以内であり住宅瑕疵担保責任保険に加入する中古住宅を購入する」という条件を満たすためには、住宅瑕疵担保責任保険に加入しつつ保険期間が切れていない築10年以内の中古住宅を購入し、なおかつ売り主から付保証明書を入手し、そのコピーをすまい給付金の申請窓口に提出しなければなりません。 - 築年数が10年以内であり建設住宅性能表示制度を利用する中古住宅
- 建設住宅性能表示制度とは、国土交通大臣が登録した登録住宅性能評価機関が住宅の建築中に耐火性、耐久性、断熱性、採光性、防音性、防犯性、バリアフリー性、メンテナンス性などを調査し、その調査結果を建設住宅性能評価書としてまとめる制度です。
建設住宅性能表示制度は住宅を建築する前に利用を申し込むことが可能であり、建設住宅性能表示制度を利用した住宅には建設住宅性能評価書が発行されます。
つまり、築年数が10年以内であり建設住宅性能表示制度を利用する中古住宅とは、築10年以内であり、なおかつ建築中に行われた現場調査によって作成された建設住宅性能評価書が付随する中古住宅というわけです。
そして、この建設住宅性能評価書のコピーは、中古住宅におけるすまい給付金の受給を申請する際の添付書類として活用できます。
よって、「築年数が10年以内であり建設住宅性能表示制度を利用する中古住宅」という条件を満たすためには、建設住宅性能表示制度を利用した築10年以内の中古住宅を購入し、なおかつ売り主から建設住宅性能評価書を入手し、そのコピーをすまい給付金の申請窓口に提出しなければなりません。
以上が「築年数が10年以内であり住宅瑕疵担保責任保険に加入する中古住宅」または「築年数が10年以内であり建設住宅性能表示制度を利用する中古住宅」の意味です。
どちらもただ単に満たすだけではなく、中古住宅の売り主から付保証明書、または建設住宅性能評価書を入手し、そのコピーをすまい給付金の申請窓口に確認書類として提出することにより条件を満たすため注意してください。
ちなみに、誰でもわかる不動産売買では、住宅瑕疵担保責任保険と住宅性能評価をわかりやすく解説するコンテンツを公開中です。
すまい給付金の申請をしつつも補助金が貰えないとお嘆きの方がいらっしゃいましたら、是非ご覧ください。
関連コンテンツ
住宅瑕疵担保責任保険とは?保険金が支払われる流れなど解説
住宅性能評価とは?費用やメリットなど解説
2. 年収が高く扶養家族が少ない
すまい給付金の受給を申請したものの補助金が貰えないとお困りであれば、年収と扶養家族に関する条件を満たさなかった可能性があります。
すまい給付金は、年収と扶養家族によって補助金の額が異なり、年収が一定額以上であったり、扶養家族の数が少なければ補助金が貰えません。
すまい給付金は、年収が低く扶養家族が多いほど支給額が増え、年収が多く扶養家族が少なければ補助金は0円となります。
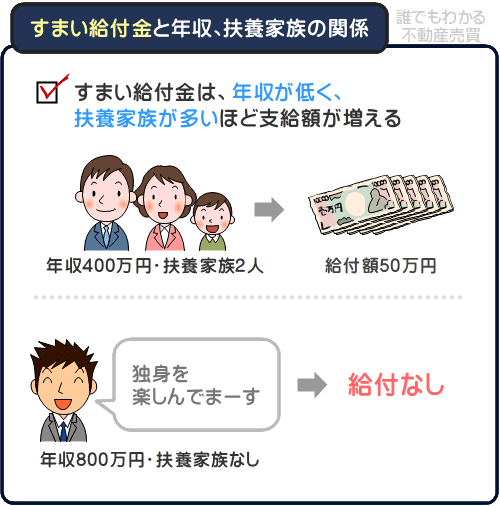
たとえば、年収が400万円であり扶養家族がお二人の場合は50万円が支給されますが、年収が800万円であり扶養家族がお一人もいらっしゃらない場合は補助金は支給されません。
すまい給付金の年収と扶養家族による受給額の目安は、以下のとおりです。
表:すまい給付金の受給額の目安
| 年収 | 扶養家族 | 支給額 |
|---|---|---|
| 400万円 | 0人 | 40万円 |
| 400万円 | 1人 | 50万円 |
| 400万円 | 2人 | 50万円 |
| 500万円 | 0人 | 30万円 |
| 500万円 | 1人 | 40万円 |
| 500万円 | 2人 | 50万円 |
| 600万円 | 0人 | 20万円 |
| 600万円 | 1人 | 30万円 |
| 600万円 | 2人 | 30万円 |
| 700万円 | 0人 | 10万円 |
| 700万円 | 1人 | 10万円 |
| 700万円 | 2人 | 20万円 |
| 800万円 | 0人 | 0円 |
| 800万円 | 1人 | 0円 |
| 800万円 | 2人 | 10万円 |
すまい給付金の受給を申請しつつも補助金が貰えない場合は、ご自身の年収と扶養家族をご確認ください。
なお、すまい給付金の具体的な受給額は「すまい給付金|すまい給付金シミュレーション」にてシミュレーションできます。
3. 中古住宅に持ち分がない
中古住宅を購入し、すまい給付金の申請を行ったものの補助金が貰えないとお嘆きの方はご存知かと思われますが、中古住宅を購入した直後は所有権移転登記を行います。
所有権移転登記とはいわゆる名義変更であり、中古住宅の購入者は所有権移転登記を行うことにより、購入した中古住宅の所有者が売り主から自分に変わったことを第三者に主張できるようになります。
この所有権移転登記ですが、売り主から自分に名義変更するのではなく、売り主から自分と自分の家族に変更したり、売り主から自分の家族のみに変更することが可能です。
しかし、すまい給付金を受給するためには、所有権移転登記の際に必ず自分の名義を入れなくてはなりません。
たとえば、売り主から自分のみ、または自分と家族に名義を変更すればすまい給付金の受給条件を満たしますが、売り主から自分の家族のみに名義を変更した場合は受給条件を満たさないといった具合です。
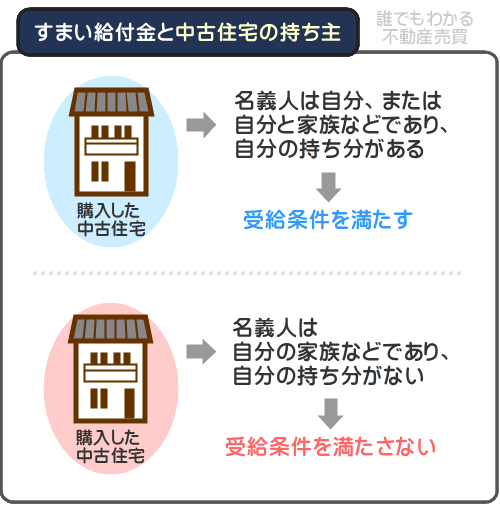
よって、すまい給付金を申請したものの補助金が貰えないのであれば、購入した中古住宅の名義にご自分のお名前が入っているかご確認ください。
購入した中古住宅の名義にご自分のお名前が入っているか否かは、登記事項証明書にて確認できます。
登記事項証明書は最寄りの法務局などで入手できますが、中古住宅を購入後に司法書士から手渡されることもあります。
また、登記事項証明書は、すまい給付金の受給を申請する際に確認書類として提出を求められます。
そのため、すまい給付金を申請しつつ補助金が貰えないとお嘆きであれば、既に登記事項証明書をご覧になっている可能性があるため留意してください。
4. 50歳未満で現金一括購入
住宅ローンを利用せず現金一括払いで中古住宅を購入し、すまい給付金を受給するためには、中古住宅の引き渡しを受けた年の12月31日の時点で50歳以上の必要があります。
そのため、現金一括払いで中古住宅を購入し、すまい給付金が貰えないのであれば、中古住宅の引き渡しを受けた年の12月31日の時点の年齢をご確認ください。
また、すまい給付金における住宅ローンの定義は、以下の条件を満たす借り入れに限られます。
- 自らが居住する住宅を購入するための資金の借り入れ
- 返済期間が5年以上の資金の借り入れ
- 知人や友人、家族、親類ではなく金融機関などからの資金の借り入れ
上記の条件を満たさない借り入れを行った場合は住宅ローンを利用したとみなされず、現金一括払いで中古住宅を購入したとみなされます。
現金一括払いで中古住宅を購入した場合は、中古住宅の引き渡しを受けた年の12月31日の時点で50歳以上でなければ、すまい給付金を貰えません。
すまい給付金が定義する住宅ローンの条件は、「すまい給付金|住宅ローンとは」にて確認することが可能です。
5. 申請書と確認書類に不備があった
すまい給付金は、一定の条件を満たした中古住宅を購入し、確認書類を添付した申請書を窓口に提出することにより受給できます。
窓口は全国に設けられ、郵送でも申請書を提出できますが、申請書と確認書類に不備があれば補助金は貰えません。
よって、すまい給付金の受給を申請したものの補助金が貰えない場合は、申請書と確認書類の不備をご確認ください。
中古住宅を購入した場合に提出すべき申請書は「すまい給付金|申請書類のダウンロード」の「中古住宅」という項目からダウンロードすることが可能であり、申請書に記入すべき主な項目は以下のとおりです。
すまい給付金の申請書の主な記入事項
- 申請書を作成した日
- 申請者本人の氏名と押印
- 購入した中古住宅の住所(購入した中古住宅に引っ越した後に発行した住民票に記載されている住所と同一の必要がある)
- 申請者本人の電話番号
- 申請者本人の生年月日
- 住宅ローンを利用した場合は借り入れ先の金融機関等の名称(金銭消費貸借契約書に記されている金融機関等の名称と同一の必要がある)
- 住宅ローンを利用した場合は金銭消費貸借契約の契約日(金銭消費貸借契約書に記されている契約日と同一の必要がある)
- 中古住宅の売り主である宅地建物取引業者の名称(売買契約書に記されている売り主の名称と同一の必要がある)
- 中古住宅の売り主である宅地建物取引業者の担当者名と電話番号(把握できない場合は記入不要)
- 中古住宅の売買契約を締結した日(売買契約書に記されている売買契約の締結日を確認しつつ記入する)
- 中古住宅の引き渡しを受けた日
- 中古住宅に入居した日(購入した中古住宅に引っ越した後に発行した住民票に記載されている転入日ど同一の必要がある)
- 中古住宅の床面積(登記簿に記されている床面積と同一の必要がある)
- 購入した中古住宅がこの記事の「1-3. 売買時等の検査」でご紹介した3つの検査項目のいずれに該当するか
また、申請書に添付すべき確認書類は「すまい給付金|申請に必要な書類について(中古住宅)」にて確認することが可能であり、詳細は以下のとおりです。
すまい給付金の申請書に添付すべき確認書類
| 書類名 | 入手先 |
|---|---|
| 購入した中古住宅に入居後の住民票の写し | 購入した中古住宅が所在する市区町村の役場 |
| 購入した中古住宅の建物部分の登記事項証明書(中古マンションを購入した場合は建物部分と土地部分の両方がまとめられた登記事項証明書) | 購入した中古住宅が所在する市町村を管轄する法務局など |
| 住民税の課税証明書 | 購入した中古住宅に転居する前に住んでいた市区町村の役場 |
| 中古住宅の売買契約書のコピー | 中古住宅の売主である宅地建物取引業者と売買契約を結んだ後に自分でコピーを取る |
| 中古住宅販売証明書 | 中古住宅販売証明書からひな型をダウンロードし、中古住宅の売り主である不動産業者に必要事項の記入を請求する |
| 住宅ローンを利用した場合は、住宅ローンの金銭消費貸借契約書のコピー | 住宅ローンを利用した銀行と金銭消費貸借契約を結んだ後に自分でコピーを取る |
| 通帳の表紙など、すまい給付金の振り込みを希望する口座の情報がわかるもののコピー | 自分でコピーを取る |
| 購入した中古住宅が「1-3. 売買時等の検査」のいずれかに該当することを証明できる書類(既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書、または震等級1以上であることが記された住宅性能評価書、もしくは住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書、建設住宅性能評価書) | 主に中古住宅の売り主である宅地建物取引業者 |
なお、上記の確認書類に含まれる「購入した中古住宅の家屋部分の登記事項証明書」は、中古住宅を購入しつつ所有権移転登記(名義変更)を行い、その手続きが完了した後の登記事項証明書をご提出ください。
所有権移転登記の手続きが完了していない登記事項証明書を提出すると、申請者と中古住宅の買い主が一致することを証明できず、確認書類として受け付けられません。
また、申請書に添付すべき確認書類は、中古住宅を購入した際のみに入手できる書類、または再発行できるものの手続きに日数を要する書類が含まれます。
よって、中古住宅を購入した際に入手した書類は捨てず、できる限り取っておくように心掛けてください。
まとめ - 国土交通省では電話サポート実施中
中古住宅を購入し、すまい給付金を申請したものの補助金が貰えないとお困りの方へ向けて、受給条件を再度確認しました。
すまい給付金は、一定の条件を満たした中古住宅を購入し、なおかつ記入漏れがない申請書に正確な確認書類を添付しつつ窓口に提出することにより受給できます。
中古住宅を購入しつつ申請を行ったもののすまい給付金が貰えないとお嘆きの方は、ご紹介した項目をもう一度ご確認ください。
特に申請書の記入漏れと確認書類の添付忘れには、注意が必要です。
すまい給付金などの補助金は、不正受給を防ぐために厳格に申請書と確認書類がチェックされます。
なお、国土交通省では、すまい給付金が上手く受給できない方へ向けて電話サポートを実施中です。
電話サポートは、すまい給付金の給付対象となる中古住宅を販売する宅地建物取引業者から入手できる「申請サポート依頼はがき」にて申し込むことが可能であり、はがきのイメージは以下のとおりとなっています。
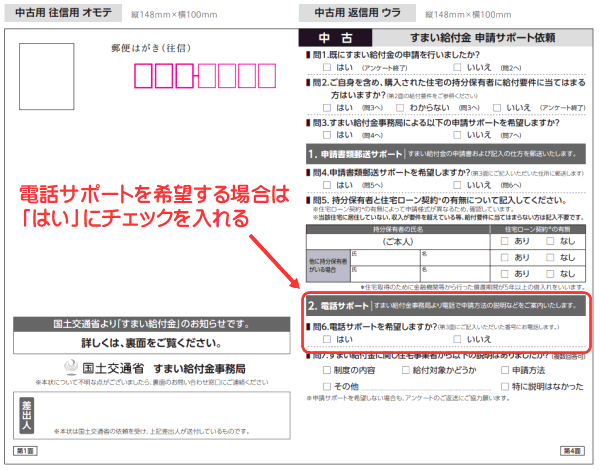
出典:国土交通省「すまい給付金について」
私がこの記事を作成する令和3年8月現在、中古住宅の購入を対象とするすまい給付金は令和3年11月30日までに売買契約を締結し、令和4年12月31日までに住宅が引き渡された場合に限り受給することが可能です。
そして、申請期限は住宅の引き渡しを受けた日から1年3ヶ月以内となっています。
皆さん、すまい給付金はリトライが可能です。ぜひお急ぎください。
ご紹介した内容が、すまい給付金が貰えないとお困りの皆様に役立てば幸いです。失礼いたします。
最終更新日:2021年8月
記事公開日:2019年7月
こちらの記事もオススメです
